あいまいさや闇から目を背けないという、現実との向き合い方

『パリの砂漠、東京の蜃気楼』 金原ひとみ 集英社 1,700円
2012年に1歳と4歳の娘とともにパリに移住した著者が、6年目の最後の1年間の生活と、テロが続き、死の影が近づく日常を恐れて突如帰国を決め、東京に戻ってからの1年間、それぞれでの暮らしをつづる。パリでの暮らしにも、帰国後の日本での暮らしにも、夫との関係にも、現実味を感じることができない中、終わりなき執筆を続ける著者の、孤独と苦悩、倦怠と怒りをヒリヒリと感じる。
これを書いている今は、緊急事態宣言が解除された直後。街には往来が増え、徐々に「店を再開しました!」という情報が、うしろめたさを含まない、ポジティブなメッセージとして届き始めた。油断は禁物だが、みんな前に進みたい、明るいほうを見たい気持ちの限界なのだと思う。しかし通常であれば健全なその志向も、今にかぎっては現実逃避かもしれない。
そんな、私たちがこのところできるだけ目を背けてきた、不安やあいまいさ、居心地の悪さ、いらだち、違和感、孤独感といったものと、真っ向から向き合い、「ちゃんと苦しんでいる」のがこの本。子供たちを連れてのフランス暮らしは、恋の悩みをあけすけにつづる友人や、日本で気にかけてくれる友人からのLINEがしょっちゅう鳴り、現地でも明るくサバサバした日本人仲間に支えられているし、東京に戻ってからのフェスと執筆の暮らしも、きっと豊かなリア充ライフとして語ることも可能だ。でもそれはポジティブという虚像だろう。自分の弱さや闇から目をそらさないことこそ、現実的であり強さなのではないか、とも思えてくる。
親の生きた時代の歴史が、私たちの中に流れている

『猫を棄てる 父親について語るとき』 村上春樹 文藝春秋 1,200円
「時が忘れさせるものがあり、そして時が呼び起こすものがある。ある夏の日、僕は父親と一緒に猫を海岸に棄てに行った。歴史は過去のものではない。このことはいつか書かなくてはと、長いあいだ思っていた」―――。著者が初めて父親の戦争体験や自身のルーツについてつづった作品。月刊『文藝春秋』で発表され、2019年文藝春秋読者賞受賞。台湾の新進気鋭のイラストレーター、高妍氏の挿絵も魅力。
大学時代、ジェンダー関連の授業で『ワイルド・スワン』を参考に、自分の母と祖母の人生を聞き、3代記にまとめるという課題が出て、ひと晩母の歴史を聞いたことがあった。昨年その母も亡くなり、今ではその原稿を残していなかったことを後悔している。自分自身がどんな歴史を内包しているのかを知ることは、アラフォー世代にとって、後半の人生を生きる大きなヒントになるのではないかと思う。
この本は村上春樹氏がそんな父の記憶の断片を語った一冊だ。幼いころ、父とともに猫を棄てに行った記憶から始まるこのストーリーは、父自身が幼少期、寺へ修行に出された話と重なり、戦争を経験した父の物語へとつながる。多くを語らなかった父ももう亡くなり、母も老いた今、知ることのできる事実は限られていたが、父の人生は確実に村上文学の土台として流れていることがわかる。
先月のGWは実家に帰れなかった人がほとんどだろうし、お盆休みも、帰省を控える日が続いているかもしれない。時々電話をして、少しゆっくりと、ご両親の物語を聞いてみてはどうだろう。自分自身について、もっと知ることがあるかもしれない。

吉野ユリ子















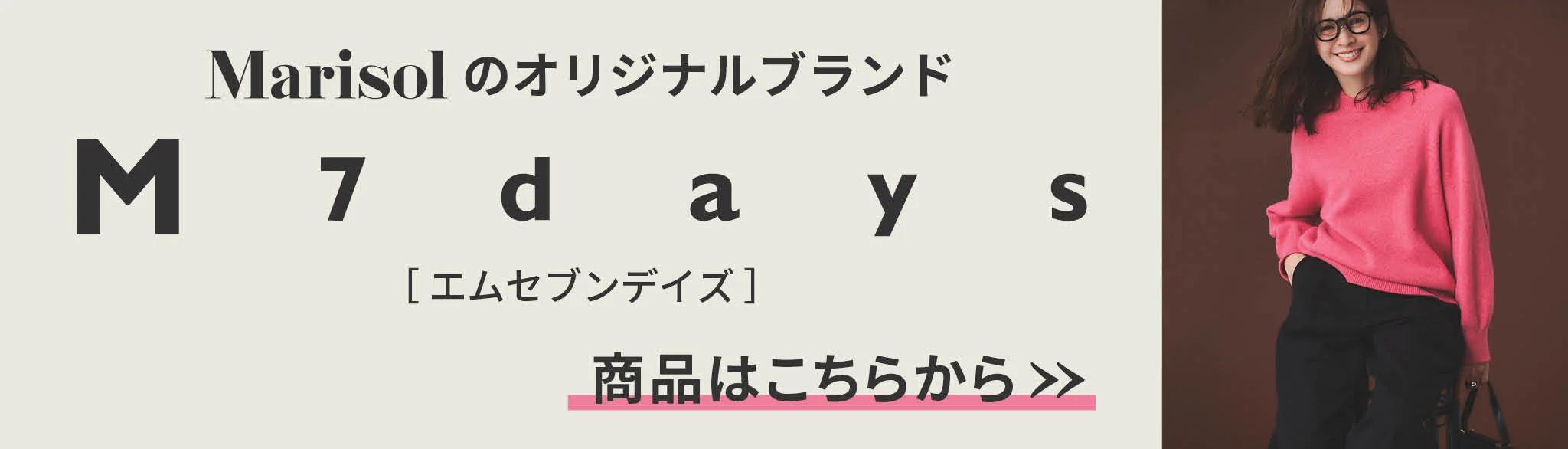




















 カタログ最新号
カタログ最新号
 特集を見る
特集を見る





























