
私は意を決して、一番上までしっかり留めてあったブラウスのボタンを2つ、パチンパチンと震える手ではずしはじめる。
「な、何? 飲んでもないのに、脱ぐ気?」
ギョッとした顔の谷原さんの前に、私は思い切って、首からぶらさげていた革ひもの先端をブラカップ付タンクトップの中からぐいっと引っ張り出し、紐の先にぶら下がったピンクのまん丸、そう「マタニティマーク」を、はいっ!と黄門様の紋どころのように3人の目の前に突き出して見せた。
「えーっ、何? 何? どういうこと? え? 須藤さん、おめでたってこと?ちょっと早く言ってよ、あたしたち、ずっと立たせっぱなしにしちゃったじゃないよ!」
仰天した谷原さんは、すごい勢いで結花ちゃんをどかせると、今更ながらずっと立ちっぱなしだった私の腕をむんずとつかんでカウンターチェアに座らせた。
「椅子冷たい? 大丈夫? あたしがさっきマスターにもっと冷やせって頼んだから、このあたりちょっと寒いかな、大丈夫? 真木、そこのブランケットとって」
わかりやすくバタバタしてくれる谷原さんは、外国人のように美しい顔の圧と違って、本当に気配りの人だ。彼女は、私のチェアを自分の方にぐるりと向けると、ひざの上にブランケットをかけてくれた。そして、私とまっすぐ向き合って話を続けた。
「ねえねえ、あなたね、話の展開がイチイチ衝撃的過ぎるんだけど、何? え? おめでたってこと? 何?どういうことよ? 性病から妊娠って、話の振れ幅大きすぎでしょ」
「ごめんなさい。そうなの、出来たの、赤ちゃん」
「ってことだよね? でもなんでそのマークが、ブラウスの中から出てくるの? 普通、バッグとか見えるところにつけるものなんじゃないの?」
谷原さんのごもっともな質問に、カウンターの向こう側で真木ちゃんと結花ちゃんも一緒にうなずいた。
「あの、なんというか、私ちょっとこのワッペンが苦手で……」
「苦手?」
そう、私は昔からこのワッペンが苦手なのだ。だいぶ昔から、ずっと人のワッペンを見るたびに思い続けていたことがある。
それはつまり……このマークは、『私はここ最近Hしました!してます!』宣言にしかみえない、ということだ。
これをバッグに着けて(中には、バッグの前後につけたりスマホにつけたり、なぜか複数個をあちこちにぷらんぷらんつけている人もいる)、彼氏だか夫らしき男性とラブラブで指を絡ませたり、べったり腕を組んで歩いている女性を見るたび、あーこの女の人はこの男の人の前で、足を開いていやらしいことしたってことなんだな……と、勝手に生々しく感じてしまい、こちらが恥ずかしくていたたまれない気持ちになり、ひとりその場から走り去る……ということが昔から実にたびたびあった。
だから、自分がその宣言マークをつけることが、どうにも恥ずかしくて、少なくともおおっぴらにはつけづらくて、ひっそり服の中にぶらさげることになっている。
……と聞いて、正面に座る谷原さんが、あ然とした顔になった。
「考え過ぎだって言われるのも、そんな風に思う人ばかりじゃないってことも、わかってるんだけど、私、自分がずっとそう見てきたからどうしても……」
「いたしてますマークに思えちゃうってこと?」
「うん」
「悪い。あたしにはほんとその感覚がわからないんだけど、それでもまあ10000歩譲って、仮にそんな風にとらえる人がいたとしてね、須藤さんにとっては、自慢の旦那さまなんでしょ? ならいいじゃない。そんな素敵な男性との間に、お子ができましたっておめでたい証ならそれはそれで。事実だし」
「そうなんだけど、でも、私と彼が裸でそういう営みをしているところを想像されたら……って思うともう恥ずかしくて恥ずかしくて」
「コワイコワイコワイ、もう怖いから! こっちが怖いって。やめてよ、そんなの考えたくないし、考えないってば! 大丈夫、誰もそんな須藤さんに興味ないから」
「理沙!」「言いかた!」
結花ちゃんと真木が即座に、本日もう何度目かの谷原さん制止のハモりが飛ぶ。
■じゃない側の女番外編記事一覧
■汗が止まらない側の女(Side真木)
【Vol.1】最近、頭もワキも汗ダクダク。色の薄いグレースーツの日なんてもう!
【Vol.2】汗を吸ったインナーのあたりが…。もしかして更年期、関係あります?
【Vol.3】再びの独り身。気づけばお惣菜にカップラーメン、冷凍食品で生き延びる日々
【Vol.4】離婚とは、噂以上に気力体力ともに消耗するものなのですね…
■酸化に負けない側の女(Side理沙)
【Vol.1】「してもらうこと」を当たり前としない女と「してもらうこと」に恐縮しない女
【Vol.2】言えない。家中の食器使いきるまでシンクに洗い物をためてしまう、なんてこと
【Vol.3】「流れに身を任せて生きる」と「無気力 / 怠惰 / 無責任」は違うのに
【Vol.4】歯のホワイトニングとブラジリアンワックス、やるならどっち先?
■現役をおりない側の女(Side結花)
【Vol.1】仕事と育児に追われる分「それ以外のこと」を激しく欲することがある
【Vol.2】50歳になっても60歳になっても絶賛恋愛中!…は、素敵です
【Vol.3】イロコイは、良い恋とか悪い恋とか言える類のものじゃない?
【Vol.4】別れた旦那からの連絡に、思わず“チッ”と毒づきました…
■恥じらいを忘れない側の女(Side慶子)
【Vol.1】思わずこらえていたものがこみあげて、無意識に両目からツーっと涙が…
【Vol.2】いくつになっても学ぶことがあるのが人生ってもので
【Vol.3】私がおかしいのか、旦那がおかしいのか、何がおかしくて、おかしくないのか
【Vol.4】生まれてこのかた経験したことがないことがわが身に起きて、ひそかにパニック…
全8話を読む >
■ご機嫌悪くない側の女(Side結花)
【Vol.1】受験、就活、婚活、妊活。どれもゴールだと思ったものは、必ず何か次のスタート
【Vol.2】自分ひとり好き勝手に生きてりゃ、誰からも感謝なんてされるわけない虚しい人生?
【Vol.3】どこで間違ったんだろう?あれ?間違ったのかな?今いるここは間違いなのか…
- 登場人物 -




















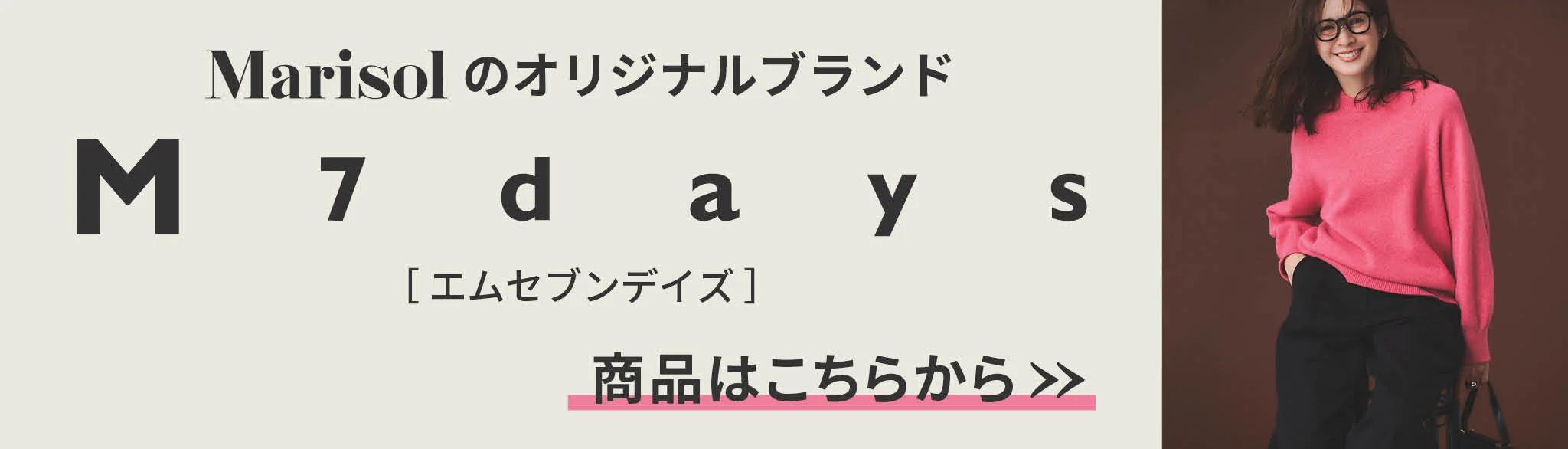




















 カタログ最新号
カタログ最新号
 特集を見る
特集を見る

































